障害者と家族について考えた時、何か支援があるのでしょうか?介護などの負担を減らせるものがあると、いいのですがね。
今回は、障害者と家族について、詳しく解説します。後半には当事者の私が経験にもとづいた内容を、記載してみました。それではいってみましょう。
障害者を支える家族のあり方
障害の有無を問わず、人間にとって「家族」はかけがえのない存在です。それは精神的・心理的さらには経済的・法律的に、強い結びつきがあります。

またわが国は代々「個人の自由」よりも、「集団の調和」を重要視する歴史的背景を有しているのです。そのことから最も身近で結合性の強い集団である「家族」という単位は、互いに助け合う共助共生の意識を強く持ちます。
これは日本人の考え方や行動様式に根強くあり、素晴らしいことなのです。
一方で個人は孤独で責められてもやむを得ない、という考えが作動してしまうこともあります。周囲へ相談したり適正な援助を受けることもできず、結果として辛くて悲しい結末に至ってしまうことさえあるのです。
家族による障害者のサポートの現状
前述のとおりわが国において障害者の家族は、「障害者をサポートするべき存在」という前提で位置づけられてきました。
裏を返せば、「障害者の家族は、障害者を扶養・世話をしなければならない」という意味でもあります。
わが国においては障害者の日常生活における支援の多くは家族が担っているというデータがあり、主な介護を担う者としては「母親」が最も多くなっています(64.2%)。実際に、私もそのような状態ですよ。

また国民生活基礎調査で得られたデータで介護保険を利用する要介護者を主に介護する者の内訳は、「配偶者」が26.2%、「子」が21.8%、「子の配偶者」が11.2%。そのうち女性が68.7%を占めています。
このことは、妻・娘・嫁という立場の家族が、介護の主要な担い手であることを示しているのです。わが国における障害者の介護やサポートの多くが、長らく女性の家族によって実施されてきたという歴史の歩みを裏付けるものであると言えるのでしょうね。
共倒れないために必要なこととは?
申し遅れましたが私は19歳の時に車の事故で首の骨を折り、頚髄を損傷して車椅子で生活しています。上記の章でも記載しましたが、日常的な介護は母にやってもらっているのです。それ以外の入浴については、ヘルパーステーションを利用していますよ。
世間は少子高齢化が急速に進展し、療養や介護を必要としながらも家族で出来ないケースが増えてきている流れがあるのです。「家族だけで障害者のサポートを完結させることが望ましい」というモデルはとうに破綻を迎えています。
私の母も70歳を迎えたため、いずれは私の介護も難しくなると思いますよ。反対に母のことで、お願いしなくてはならないことになるかも・・・。
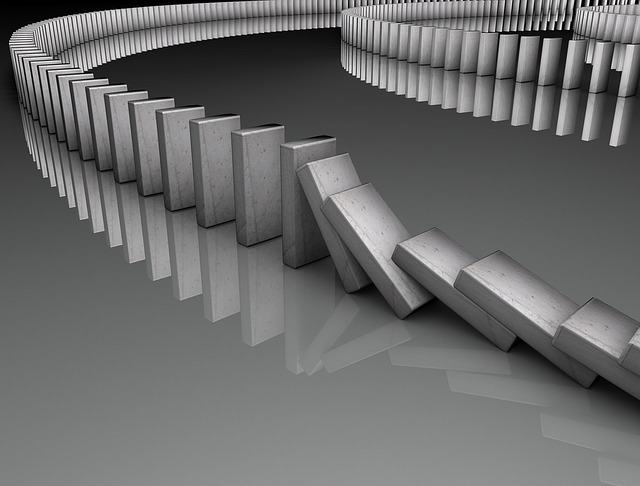
そこで共倒れを避けるために、柔軟な考え方で障害者サポートに臨む姿勢が求められるでしょうね。
私の経験から言えば、まず考えられるのが福祉サービスの相談。過去に詳しく書いた記事があるので、お時間がある際にお読みいただけるとありがたいです。

記事内にも書きましたが、「市役所にある福祉課もしくは福祉事務所に相談する」ことが先決です。私は母の手術による入院でありがたいサポートをしてもらい、本当に助かりましたからね。
手伝ってもらうことは何も難しいことではありませんし、恥ずかしいことでもないのです。まずは電話でいいので、今の状況を伝えればいいだけですよ。
状況がわかれば、あとはいろいろ考えてくれます。後日に訪問されて、直接会話になりますよ。サポートしてもらうだけで、本当に助かりますからね。
「困ったときは互いに助け合う。」というわが国に特に強く根付いている考え方は、非常に美しく素晴らしいものです。それを「家族」という小さな枠だけに限って考えてしまうと、介護者と障害者を追い詰めてしまうことになってしまいます。
家族での当事者サポートに当たる人は、困ったときは一人で抱え込まずに外部の相談機関や専門機関が相談に乗ってくれるということを覚えておくといいですよ。それがする側される側双方の人生に、幸せをもたらすことに必ずやつながるはずです。陰ながら応援していますね。
まとめ
にほんブログ村
応援お願いしますm(_ _)m
障害者と家族は、切っても切り離せないものです。だけど、人というのはいづれ老いていくもの。一生という言葉にも、限界がありますからね。いざという時のことを考えていれば、何かと気も楽になりますよ。弱者にやさしい社会が生まれることを、願っております。



コメント